前回、データセンタ周りの半導体に係る話が俄かに良い意味で騒がしくなってきましたということをお伝えし、ひとまずインテルの動きについて概説させて頂きました。
今回はその時に頭出しさせて頂いたクアルコム(QCOM)の話について触れていきたいと思います。
クアルコムとアップルが和解が示す、クワルコムの技術優位性
まずその前に最新のホットな話としては、もうニュースでお聞き及びだと思いますが、クアルコムがアップルと2017年初めから争っていた訴訟に終止符を打ち和解、今後は再び5Gの為に特許ライセンス契約を結び、更には複数年のチップセット供給を受けることに合意したと発表しました。これを受けてクアルコムの株価は急騰しました。
ワイヤレス関連の技術は一朝一夕にはたとえインテルといえども容易に開発が出来るものではありません。それが証拠に、アップルはクアルコムのライセンスが使えなくなってしまった対応策として、インテルに5G用のチップを作ることを依頼していましたが、結局インテルには無理だったようです。というか、たぶん時間が掛かり過ぎるということになったのでしょう。
とは言え、アップルは5Gで他社の後塵を長く拝するわけにはいきません。事実、クアルコムは昨年末に5Gに対応したスマホ用のCPU「Snapdragon 855」を既に発表済みで、サムスンの「Galaxy S10」などには既に搭載されているのです。インテルを待つ限り、年内にiPhoneは5Gに対応できないというのは許されなかったのでしょう。
クアルコムとアップルはここに和解の道を選びました。条件的にはクアルコムにかなり有利なようだと噂されています。更に、和解の翌日、インテルは5Gモデムの開発からの撤退を表明しています。それだけワイヤレス技術というのは難しいものだとも言えます。
データセンタのボトルネックを解消する動きが続々と
さて、話は本題に戻ってデータセンタ向けのCPUの話です。実はクアルコムが発表した「Cloud AI 100」というのは、CPUというのともちょっと違います。データセンタのサーバーなどを想定したAI処理向け専用のプロセッサーということになります。アクセラレーターと呼ばれる場合もありますが、AI推論処理の高速化を目的に開発された特別な半導体ということです。
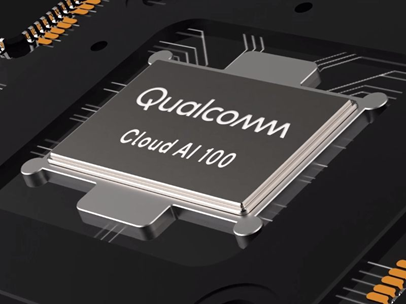
なぜ、クアルコムがこの「Cloud AI 100」を発表したことに意義があるかと言えば、前述したスマホ用のCPU「Snapdragon 855」などのシリーズに代表されるように、クアルコムの今までのお得意分野はスマホなどの携帯端末向けのCPUです。
パソコンでも、データセンタでも、その中で稼働するCPUは通常電源と繋がっており、バッテリー消費を気にする必要はありません。一方、スマホなどの携帯端末などの場合、利用できる電力はバッテリーから供給されるため、低消費電力というのは開発当初のDNAから組み込まれた基本的な性格です。
昨今のデータセンタの大きなニーズの一つは「低消費電力」であることは以前にもお伝えしました。また電力を沢山消費すると、当然発熱量が増大します。これらがボトルネックになっています。高性能なCPUが沢山並んで、電力をガンガン消費すれば、併せて発熱も相当なレベルになるため、空調を含めて冷却という事が大事な意味を持ってきます。
しかし低消費電力であれば、自ずと発熱も抑えられるため、データセンタのコスト面でも非常に有利になるといえます。
実は詳細はまだ発表されていない
パソコンやサーバー向けのCPUに取り組んできたインテルは、その回路の設計に関して「インテル・アーキテクチャー」と呼ばれる独自の世界を持っています。一方、スマホのCPUである「Snapdragon」などを開発してきたクアルコムのそれは、ソフトバンクグループが買収したARM社が開発した「ARMアーキテクチャー」というものが基本になっています。恐らく、クアルコムの今回の製品もARMアーキテクチャーを利用していると思われます。
インテルがCPUの世界の雄であることは疑いのない事実ですが、なぜスマホの世界まで席巻出来なかったかと言えば、このアーキテクチャーの違いによって、低消費電力・低発熱というCPUを開発出来なかったからです。
ATOMと呼ばれるシリーズなど、何度もトライし、Windows Phoneなどに採用されたこともあったと思いますが、普及しなかったのにはそれなりな理由があるわけです。スマホなどの携帯端末にはARMアーキテクチャーの方が優れて向いていたということです。
クアルコムが大きな世界を狙ってきた
同社のWebサイトを見ると、下の絵のように、明確に「クラウドAI推論ニーズを満たすように設計されたAIソリューションを作成しました」と書かれています。

ただ、まだ試作品が2019年後半に登場予定で、2020年から量産開始を目指している段階ですから、実際に量産開始の時には他社に負けているという可能性は否定できません。
とは言え、今回のクアルコムの発表が、エヌビディアの独走態勢に対する業界からの大きな挑戦状ともとれ、またそれはこの業界を益々活況にして技術進歩を齎すことを意味しているという事が重要です。技術の進歩は決して止まらないし、後戻りはしませんから。
クアルコムはファブレス(半導体製造工場を持たない半導体メーカー)で、今回もファンダリー(半導体の製造を専門に行う会社)である台湾のTSMCと組んで、デザインルール7㎚で作る予定でいるようです。
量産が2020年ならば、多くの準備は2019年中に始まります。最先端デザインルールの半導体生産の立ち上げは、所謂「垂直立ち上げ」は不可能だからです。ということになれば、半導体製造装置メーカーへの発注はパイロット生産の始まるよりもっと前ということになり、だからこそ、こうした流れを追う事で多くの投資機会が見えてくるということです。是非、注目を怠りなくしていきたい会社です。



